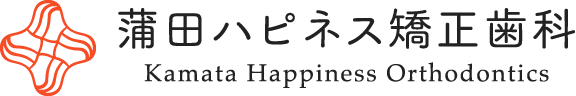歯科矯正による知覚過敏はなぜ起こる?その対策
歯科矯正による、知覚過敏の原因について
歯の移動による知覚過敏
歯が動く際、歯根膜や歯髄(歯の神経)が圧迫・刺激されて知覚過敏が起きてしまいます。
ワイヤー矯正では、ワイヤーの調整直後、マウスピースに交換した後に起こりやすいです。
歯のエナメル質の摩耗
歯が動くことで一時的に噛み合わせが変わり、特定の歯に負担がかかることがあります。
強い噛みしめや歯ぎしりの影響で、エナメル質がすり減ると象牙質が露出し、知覚過敏が生じることがあります。
歯肉の退縮
矯正中に歯肉が少し下がることがあり、歯の根元が露出すると知覚過敏が起こりやすくなります。
加齢や歯ブラシの強い摩擦によって歯茎が下がり、象牙質が露出してしまうことがあります。
きつ状欠損(WSD)
噛む力の応力がエナメル質と象牙質の境目に集まり、歯が欠けてしまうことで歯に刺激が加わりやすくなります。
口腔内環境の偏差
矯正装置がついていると歯磨きがしにくくなり、歯垢がたまりやすくなります。
磨き残しが増えることで、歯茎の炎症(歯肉炎)や歯の脱灰(表面のミネラルが溶ける現象)が起こり、知覚過敏を感じやすくなります。
知覚過敏の対策
① 知覚過敏用の歯磨き粉を使う
硝酸カリウムやフッ素が配合された歯磨き粉(シュミテクトなど)を使うと、歯の神経の過敏な反応を抑えることができます。
② 柔らかい歯ブラシを使う
硬い歯ブラシや強すぎるブラッシングはエナメル質を削ったり、歯茎を傷つけたりするため、「やわらかめ」の歯ブラシを使いましょう。ただ、ワイヤー矯正の場合はワイヤーの下が磨きにくいため、ワイヤーの下を小刻みに優しく磨くことが大切です。
③ フッ素塗布
フッ素入りのマウスウォッシュを使用したり、歯科医院で高濃度フッ素塗布を受けたりすることで、歯の表面を強化し、知覚過敏を抑えることができます。
④ 矯正装置の調整を相談
痛みが強い場合は、矯正力を少し緩和することも可能ですのでご相談ください。
⑤ 知覚過敏の進行を防ぐ生活習慣
酸性の飲食物(炭酸飲料、柑橘類、酢の多い料理)を控えてみてください。
酸性の食品はエナメル質を溶かしやすくするため、摂取後はすぐに口をゆすぐようにしてください。